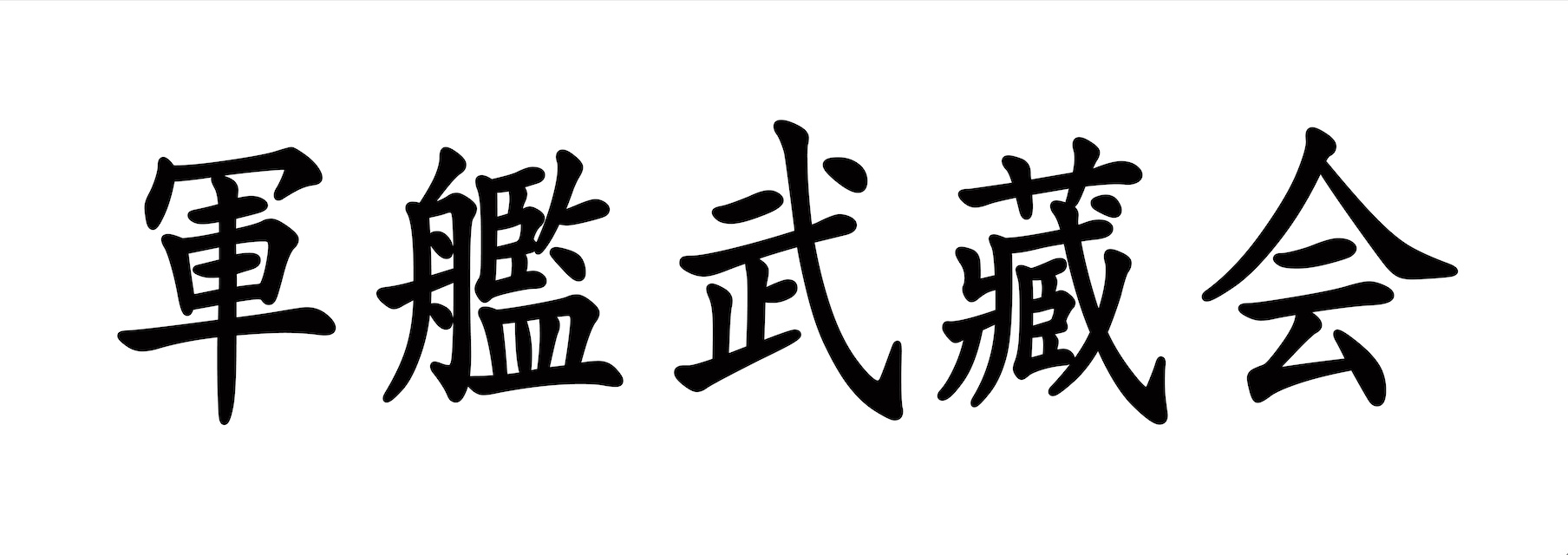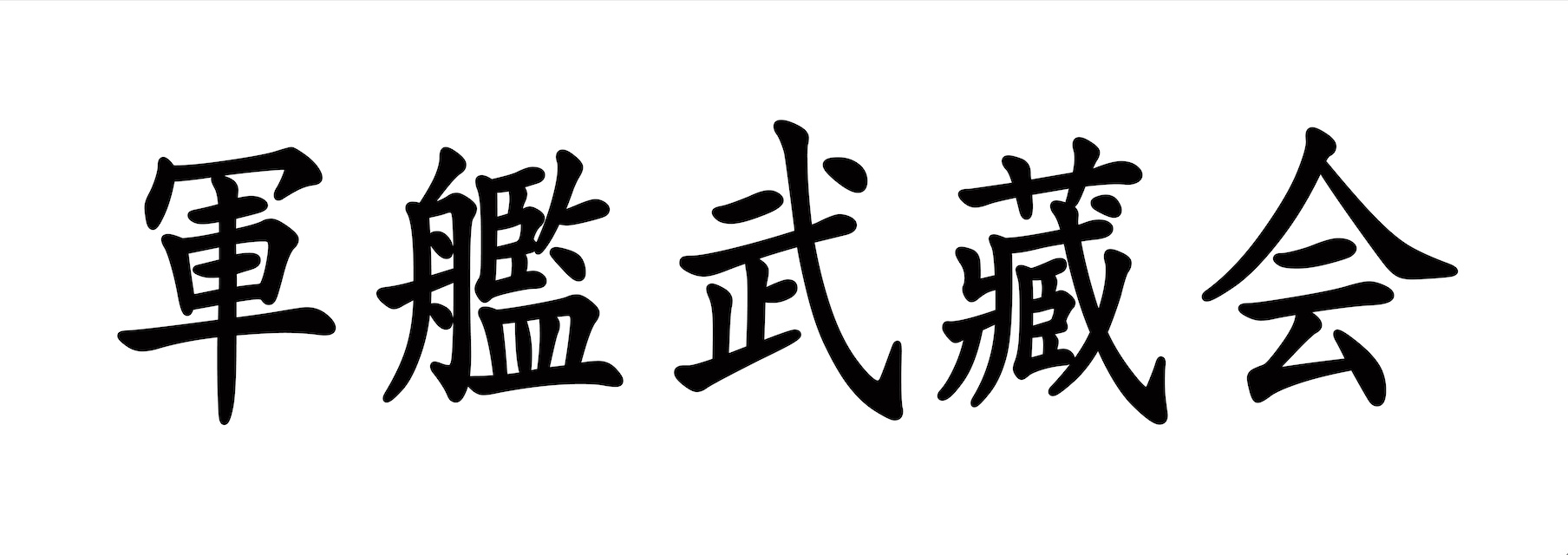 資料集 ~武藏あれこれ~
資料集 ~武藏あれこれ~
〇何故、「戦艦武蔵」ではなく「軍艦武藏」と呼称するのか
戦艦という名称は、大は戦艦や航空母艦、小は駆逐艦や潜水艦などの艦種を示す用語である。ただし、これら海軍が所有する艦艇のすべてが、軍艦とは呼ばれない。戦艦や航空母艦、巡洋艦までの、大型で戦闘能力が高く、海上作戦の主軸になるのが軍艦で、視覚的には艦首に天皇から拝受した菊の御紋章を輝かせているのが軍艦だが、例外もある。
僅か五〇〇トン前後の排水量しかないちっぽけな河川用の砲艦も、御紋章を戴く軍艦の部類に入る。理由は艦内に外交施設や貴賓室を備えた領事館の役割を果たすといったことで、格式が高い艦だからである。
艦長の呼び方にも格差があって、軍艦に該当する「武藏」や「大和」だと、「武藏艦長」や「大和艦長」と艦名を用いるが、軍艦以外の艦艇は艦名を外されて、「駆逐艦長」とか「潜水艦長」と呼ばれた。
〇世界最大の「大和」型戦艦
海軍では基本的に、同じ型の艦(同型艦)を別々の造船所で、同時に二隻建造することで、同一の設計図を基に、同じ材料が使用される。また二箇所の造船所職員が建造のための特殊技術や技能を共有でき、建造から艤装までの期間、問題点や改良点などの検討対処が迅速に行われ、これによって経費を抑え、工期の期間短縮を可能にできる。同型艦の強みはそれだけではなく、推進力や攻撃力が同一なので、艦隊運動はより円滑で正確になり、結果的には戦力の増強につながる。
同型艦の「武藏」と「大和」は、「姉妹艦」である。妹の「武藏」は、姉の「大和」より八か月余り遅れて誕生した。この「大和」型戦艦が、現在でも高い人気を誇っているのは、シルエットの美しさもさることながら、空前絶後の砲力と防御力を備えた世界最大の巨艦だったからだろう。以下に主要な諸元を紹介する。
全長 二六三メートル
最大幅 三八・九メートル
公試排水量 六万九〇〇〇トン
基準排水量 六万四〇〇〇トン
満載排水量 七万三〇〇〇トン
最大速力 二七ノット(時速約五〇キロ)
当時の世界海軍を見渡しても、これほど巨大な軍艦は存在しなかった。また現在では戦艦を運用する国はなく、したがって「武藏」と「大和」が世界最大の超弩級戦艦ということになる。主砲は四六センチ砲三連装を三基、計九門を搭載している。アメリカ海軍で一番大きなアイオワ級戦艦(基準排水量四八四二五トン)の主砲は、四〇・六センチと一回り小振りである。また主砲弾の重量を比較すると、大和型は一四六〇㎏で、これに対してアイオワ級は一二〇〇㎏と小さく、当然破壊力は劣る。
それでは「大和」型とアイオワ級の戦艦が、一対一で砲戦を演じたら結果はどうなるだろうか。大和型は砲弾の大きさに加えて、射程距離は約四万二〇〇〇メートルと、水平線の遥か彼方まで飛ばせる。一方のアイオワ級は約三万八〇〇〇メートルまでしか届かない。となると、勝敗はおのずと決してしまう。それでも仮にアイオワ級が射程内にまで踏み込んで、「大和」型に砲弾を命中させたとしよう。ところが、大和型船体の主要箇所には分厚いアーマー(装甲鈑)が張り巡らされているので、砲弾は貫通できずに跳ね返されてしまう。計算上では、本艦が搭載する四六センチ砲弾でなくては、「大和」型に致命傷を与えられない。
したがって「武藏」乗員のほとんどは、「絶対不沈艦」だと信じて、来るべき海戦に臨んだのだった。
〇「武藏」の航跡と乗組員たちの足跡
昭和十七年八月五日、呉軍港での竣工引渡式を終えて、「武藏」は誕生した。以降、聯合艦隊主隊に編入された「武藏」は、トラック島泊地に二度、パラオ泊地に一度、入港するが、戦闘の機会に恵まれずに、日だけが空しく経過していった。この間、聯合艦隊旗艦になり、山本五十六大将が司令長官として「武藏」に着任した。だが、二か月も経たない十八年四月十八日に、ブーゲンビル島上空で山本長官搭乗の一式陸攻が撃墜され、長官は戦死を遂げた。
二日後には古賀峯一大将が、聯合艦隊司令長官の職を継いだ。だが十九年三月三十一日、古賀長官も司令部職員と二式大艇でフィリピンのダバオに移動中、低気圧に巻き込まれて遭難、殉職してしまった。
「武藏」がはじめて実戦を経験したのは、六月十九日から二十日にかけて生起した「マリアナ沖海戦」の時だった。「武藏」は日本機動部隊の前衛部隊として、サイパン西方に遊弋する敵機動部隊の撃滅を目指して進撃していた。海戦二日目、来襲する敵機に対してはじめて四六センチ主砲を発射した。しかし、敵機撃墜の記録はなく、「武藏」にも被害はなかった。
十月二十四日、「武藏」の属する栗田艦隊主隊(第一遊撃部隊)は、米軍が上陸したフィリピン・レイテ湾に向けて、シブヤン海を航行していた。午前十時三十分、米機動部隊が放った戦爆雷合同の攻撃隊が、栗田艦隊に対して攻撃を開始した。
対空戦闘は熾烈だった。寄せ来る敵機に、「武藏」の対空火器はあらん限りの弾丸を放って対抗した。だが圧倒的な数の攻撃機の猛攻に、「武藏」の被害は回を重ねるたびに増大していった。やがて第五次対空戦闘を迎えた時には、「武藏」の艦首は深く沈み、船体は左に大きく傾いた状態で、速力は一七・五ノット(時速約三二キロ)にまで低下した。
空襲は止んだが、喘ぐように航進を続ける「武藏」に、主隊とともに行動する力は残されていなかった。二隻の駆逐艦に護衛された「武藏」は、コロン湾に向けて避退行動を開始しようとしたが、洋上にほぼ漂泊状態になってしまった。
午後七時三十分を過ぎて、ついに乗員に対して「総員退去」の退艦命令が下されたが、時はすでに遅かった。急激に船体が左に大きく傾くと同時に、艦首から棹立ちになった格好で次第に海中に没していった。七時三十五分、「武藏」は二年二か月余の生涯を閉じた。
夜の海に投げ出された乗員たちの、重油にまみれた必死の漂流がはじまった。護衛の駆逐艦「濱風」と「清霜」の溺者救助作業は、五時間半に及んだ。この間、多くの乗員たちが重油にまみれた状態で海中に沈んだ。
翌二十五日、午前一時三十分に救助作業は終了し、収容者を満載した二隻の駆逐艦は、マニラ湾に向かった。この時救われた「武藏」乗員は一三七六名に及んだ。だが、九死に一生を得た彼らの行く手には、さらなる過酷な運命が待ち構えていた。
元乗員を乗せて内地へ向かった輸送船は、敵潜水艦の雷撃によって約三〇〇名の戦死及び行方不明者を数えた。さらには、マニラ方面に残留させられた者たちは、陸上戦によって六四一名が戦病死した。
結局、生きて祖国の土を踏めたのは、出撃時の乗員、二三三九名の内、約四五〇名でしかなかった。
軍艦武蔵会顧問 手塚正己